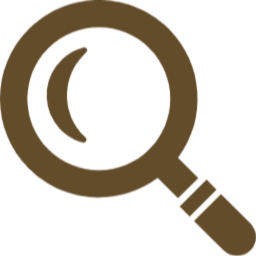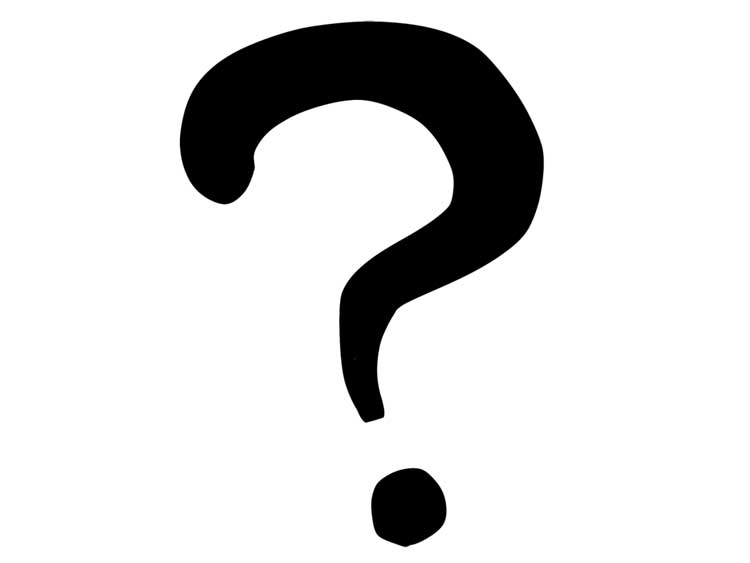
お寺にまつられている仏像の中でも、限られた日にしか会うことのできない「秘仏」。
仏像は本来、拝むためにつくられたものですが、なぜ秘仏があるのでしょうか?
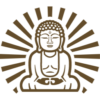
1.秘仏とは
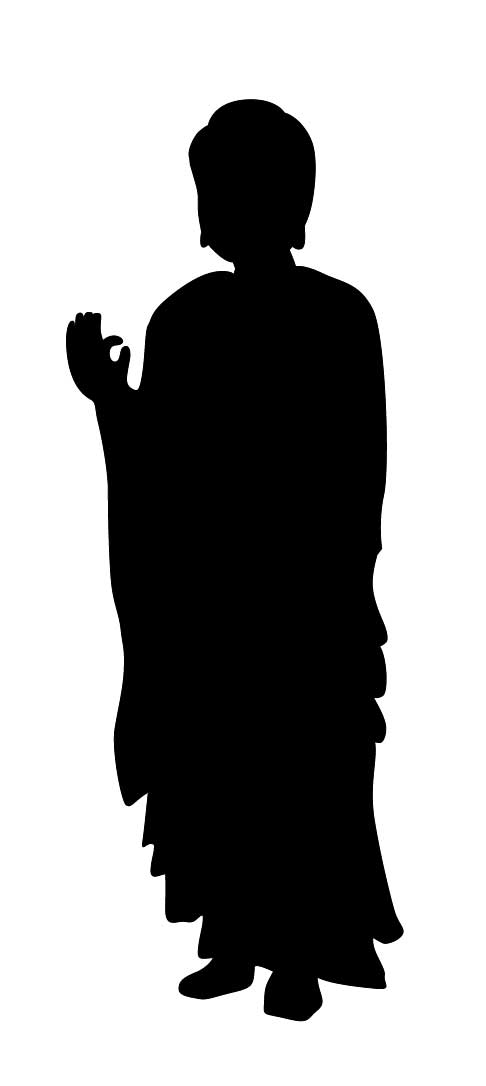
秘仏とは、
さまざまな理由によって、ふだんは姿を見ることのできない仏像
のこと。
仏像が納められている大きな箱を厨子といい、厨子の正面には扉がついています。
お寺で目にする仏像の多くは、この扉が開いた状態でまつられています。
一方、秘仏をまつる厨子の扉は固く閉ざされているため、その姿を見ることができません。
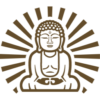
秘仏はふだん見ることができませんが、特別に公開されることがあります。
秘仏を特別に公開することを開帳(かいちょう)または御開帳(ごかいちょう)といい、開帳の仕方には以下のパターンがあります。
①定期的に公開
「60年に一度」「12年に一度」「毎年春ごろ」など、決まった時期に開帳。
②不定期に公開
原則非公開であるが、臨時で開帳されることがある。
③永久に非公開
「絶対秘仏」とよばれ、住職でさえも姿を見ることができず、永久に開帳されない。
また、秘仏をまつる厨子の前には、秘仏の身代わりとしてお前立ちとよばれる像が置かれていることがあります。
お前立ちは秘仏と同じ姿をしていることが多く、お前立ちのみ拝観できる場合もあれば、お前立ちさえも隠されているケースもあります。
2.隠す理由
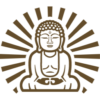
(1)信仰上の理由
仏像の素材には、神木(神さまが宿る大きな木)とよばれる不思議な木が使われることがあります。
日本では古くから「神さまは姿を現わさない」と信じられてきたため、神木から彫られた仏像(仏さま)も神さまと同じように隠されていたと考えられます。
-

-
あわせて読みたい「神」と「仏」の違いをイラストでやさしく解説
初詣、七五三、神社・お寺の縁日、秋祭り、すす払い…… 日本には季節ごとにさまざまな行事があり、神さまや仏ほとけさまに幸せを願ったり、地域の人たちが集まってお祭りを行ったりします。
続きを見る
また、
- 仏さまは人間とは別の世界に住んでいるため、あえて遠ざけている。
- 仏さまの強すぎる力(ご利益)をコントロールするために、扉を固く閉ざしている。
などの説もあります。
(2)防犯上の理由
秘仏となる仏像には歴史的・芸術的にすぐれているものが多く、盗難を防ぐために隠しているケースもあります。
(3)保存上の理由
木の仏像は光・湿気・虫などに弱く、傷んだり彩色が落ちたりするのを防ぐために秘仏にしているケースも多くあります。
このような理由で隠されている秘仏の中には、地域のイベントに合わせて開帳し、保存状態の確認や換気をしているものもあります。
3.秘仏にまつわる知識
(1)秘仏に多い仏像
秘仏となる仏像はさまざまですが、中でも
などが多い傾向があります。
これらの仏は人びとに絶大なご利益をもたらすことから、昔から密教の儀式に用いられてきました。
密教(みっきょう)とは
仏教とヒンズー教が融合して生まれた、不思議な宗教。
「真言」とよばれる呪文や、「護摩」とよばれる火をたく儀式などが特徴。
大日如来と一体になることによって、人は生きたまま仏になれると説いている(即身成仏)。
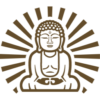
たとえば、
- 十一面観音なら「十一面法」(疫病封じの儀式)
- 弁財天なら「弁財天秘法」(金運を呼びこむ儀式)
というふうに、それぞれが得意分野をもちます。
このように、いざというときのためのご利益をもたらす大事な存在であることから、ふだんは隠されていたと考えられます。
(2)開帳のサイクル
定期的に公開される秘仏は、
- 60年に一度
- 50年に一度
- 33年に一度
- 12年に一度
- 1年に一度(または数回)
というふうに、開帳のサイクルが定められています。
「60年に一度」は陰陽五行という古代中国の思想において重要な意味をもつ数字“60”に由来し、「33年に一度」は観音菩薩の変身する33の姿にちなむもの。
「12年に一度」は干支にちなむ仏像をその年に開帳しようというものであり、うま年の馬頭観音が代用的な例。
「1年に一度」は、縁日での開帳。
縁日とは仏と縁を結ぶための大切な日であり、この日にお参りすると、さらなるご利益があるといわれています。
なお、「60年に一度」や「33年に一度」は次の開帳までの期間があまりにも長いため、その真ん中の年で特別に開帳することがあります。
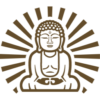
4.日本の主な秘仏
開帳日は変更になる場合があるため、訪問前には必ず各自でご確認ください。
東北
| お寺 | 仏像名 | 開帳日 |
|---|---|---|
| 上宇内薬師堂(福島) | 薬師如来坐像 | 不定期(要予約) |
| 弘安寺(福島) | 十一面観音菩薩立像 | 毎年8月9日・10日(おこもり大祭)、11月1日~10日(菊祭り大祭) |
| 勝常寺(福島) | 薬師如来坐像 | 毎年4月1日~11月15日(要予約) |
関東
| お寺 | 仏像名 | 開帳日 |
|---|---|---|
| 常楽院[高山不動尊](埼玉) | 軍荼利明王立像 | 毎年4月15日、12月の冬至 |
| 新勝寺[成田山](千葉) | 不動明王坐像および二童子立像 | 10年に一度 |
| 大観音寺(東京) | 観音菩薩像頭部 | 毎月11 日・17日 |
| 塩船観音寺(東京) | 千手観音立像 | 毎年1月1日~3日(元旦祭) |
| 浅草寺(東京) | 聖観音菩薩立像 | 絶対秘仏、お前立ちは毎年12月13日 |
| 増上寺(東京) | 阿弥陀如来立像[黒本尊] | 毎年1月15日、5月15日、9月15日 |
| 称名寺(神奈川) | 弥勒菩薩立像 | 毎年2月31日~1月3日、8月2日 ※要確認 |
| 宝条坊(神奈川) | 薬師三尊像 | 毎年1月1日~3日、1月8日(初薬師)、4月15日(春季例大祭) |
北陸・中部
| お寺 | 仏像名 | 開帳日 |
|---|---|---|
| 妙高寺(新潟) | 愛染明王坐像 | 毎年1月1日~3日、6月第2土曜日(愛染明王大祭)、毎月26日(月例祭) |
| 茂林寺(新潟) | 地蔵菩薩半跏像 | 毎年5月7日・8日(花祭り) |
| 安居寺(富山) | 聖観音菩薩立像 | 毎年10月18日 |
| 意足寺(福井) | 千手観音菩薩立像 | 12年に一度(とら年)、ただし事前予約で拝観可能 |
| 為星寺[加茂神社](福井) | 千手観音菩薩立像 | 33年に一度 |
| 正林庵(福井) | 如意輪観音菩薩半跏像 | 毎年9月17日、ただし事前予約で拝観可能 |
| 中山寺(福井) | 馬頭観音菩薩坐像 | 33年に一度(中開帳は17年に一度)、ただし毎年2月3日の星供養(要予約)の際に拝観可能 |
| 馬居寺(福井) | 馬頭観音菩薩坐像 | 24年に一度(うま年)、中開帳は12年に一度 |
| 甲斐善光寺(山梨) | 阿弥陀三尊像 | 数え年で7年に一度(うし年・ひつじ年) |
| 善光寺(長野) | 阿弥陀三尊像 | 絶対秘仏、お前立ちは数え年で7年に一度(うし年・ひつじ年) |
| 美江寺(岐阜) | 十一面観音菩薩立像 | 毎年4月18日 |
京都・奈良
| お寺 | 仏像名 | 開帳日 |
|---|---|---|
| 海住山寺(京都) | 四天王立像 | 毎年秋ごろ |
| 清水寺(京都) | 千手観音菩薩立像 | 33年に一度、お前立ちは常時拝観可能 |
| 広隆寺・本堂(京都) | 聖徳太子立像 | 毎年11月22日 |
| 広隆寺・霊宝殿(京都) | 薬師如来立像 | 毎年11月22日 |
| 浄瑠璃寺(京都) | 吉祥天立像 | 毎年1月1日~15日、3月21日~5月20日、10月1日~11月30日 |
| 神護寺(京都) | 五大虚空蔵菩薩坐像 | 毎年5月13日~15日、10月の3日間(第2月曜日・祝日を含む) |
| 清凉寺・本堂(京都) | 釈迦如来立像 | 毎年4月・5月・10月・11月、毎月8日 |
| 清凉寺・霊宝館(京都) | 十大弟子立像 | 毎年4月・5月・10月・11月 |
| 大報恩寺(京都) | 釈迦如来坐像 | 毎年8月7日~10日(六道参りの期間) |
| 仁和寺(京都) | 薬師如来坐像 | 不定期 |
| 報恩寺(京都) | 厨子入千体地蔵菩薩像 | 不定期(要予約) |
| 六波羅蜜寺(京都) | 十一面観音菩薩立像 | 12年に一度(たつ年) |
| 秋篠寺(奈良) | 大元帥明王立像 | 毎年6月6日 |
| 金峯山寺(奈良) | 蔵王権現三尊像 | 毎年春ごろ、秋ごろ |
| 興福寺・南円堂(奈良) | 不空羂索観音菩薩坐像 | 毎年10月17日 |
| 興福寺・北円堂(奈良) | 弥勒如来坐像および無著・世親立像 | 毎年春ごろ、秋ごろ |
| 五劫院(奈良) | 五劫思惟阿弥陀仏坐像 | 毎年2月12日~18日、8月1日~12日、10月5日、ただし事前予約で拝観可能 |
| 西大寺(奈良) | 愛染明王坐像 | 毎年1月15日~2月4日、10月25日~11月15日 |
| 正暦寺(奈良) | 薬師如来倚像 | 毎年4月18日~5月8日、11月初旬~12月初旬、12月22日 |
| 大安寺(奈良) | 馬頭観音菩薩立像 | 毎年3月1日~31日 |
| 伝香寺(奈良) | 地蔵菩薩立像 | 毎年3月12日、7月23日、ただし事前予約で拝観可能 |
| 唐招提寺(奈良) | 鑑真和上坐像 | 毎年6月5日~7日、お前立ちは常時拝観可能(開山堂にて) |
| 東大寺・二月堂(奈良) | 十一面観音菩薩立像 | 絶対秘仏 |
| 東大寺・法華堂(奈良) | 執金剛神立像 | 毎年12月16日 |
| 法隆寺・上御堂(奈良) | 釈迦三尊像 | 毎年11月1日~3日 |
| 法隆寺・夢殿(奈良) | 観音菩薩立像[救世観音] | 毎年4月11日~5月18日、10月22日~11月22日 |
| 法華寺(奈良) | 十一面観音菩薩立像 | 毎年3月20日~4月7日、6月5日~10日、10月25日~11月10日(年によって若干異なる) |
関西(京都・奈良以外)
| お寺 | 仏像名 | 開帳日 |
|---|---|---|
| 観菩提寺(三重) | 十一面観音菩薩立像 | 33年に一度 |
| 延暦寺(滋賀) | 薬師如来立像 | 不定期、お前立ちは常時拝観可能 |
| 千手院[川道観音](滋賀) | 千手観音菩薩立像 | 33年に一度(中開帳は17年に一度)、お前立ちは毎年11月4日 |
| 願成就寺(滋賀) | 十一面観音菩薩立像 | 49年に一度(中開帳は25年に一度)、ただし事前予約で拝観可能(10人以上30人以下の団体に限る) |
| 盛安寺(滋賀) | 十一面観音菩薩立像 | 毎年1月1日~3日、4月29日~5月5日、5月・6月・10月の毎週土曜日 |
| 福林寺(滋賀) | 十一面観音菩薩立像 | 毎年11月初旬 |
| 櫟野寺(滋賀) | 十一面観音菩薩坐像 | 毎年4月19日~5月第2日曜日、10月19日~11月第2日曜日 |
| 愛染堂[勝鬘院](大阪) | 愛染明王坐像 | 毎年1月1日~7日、6月30日~7月2日(愛染まつり) |
| 勝尾寺(大阪) | 千手観音菩薩立像 | 毎月18日 |
| 観心寺(大阪) | 如意輪観音菩薩坐像 | 毎年4月17日・18日 |
| 道明寺(大阪) | 十一面観音菩薩立像 | 毎年1月1日~3日、4月17日、毎月18日・25日 |
| 葛井寺(大阪) | 千手観音菩薩坐像 | 毎年8月9日(千日まいり)、毎月18日 |
| 野中寺(大阪) | 弥勒菩薩半跏像 | 毎月18日 |
| 温泉寺(兵庫県豊岡市) | 十一面観音菩薩立像 | 毎年4月23日・24日(温泉まつり) |
| 神呪寺(兵庫) | 如意輪観音菩薩坐像 | 毎年5月18日 |
| 中山寺(兵庫) | 十一面観音菩薩立像 | 毎月18日 |
| 紀三井寺(和歌山) | 十一面観音菩薩立像および千手観音菩薩立像 | 50年に一度 |
| 高野山 ・南院(和歌山) | 不動明王立像[波切不動] | 毎年6月28日 |
| 粉河寺(和歌山) | 千手観音菩薩立像 | 絶対秘仏 |
| 慈尊院(和歌山) | 弥勒如来坐像 | 21年に一度 |
| 補陀洛山寺(和歌山) | 千手観音菩薩立像 | 毎年1月27日、5月17日、7月10日 |
中国・四国
| お寺 | 仏像名 | 開帳日 |
|---|---|---|
| 摩訶衍寺(広島) | 十一面観音菩薩立像 | 33年に一度(中開帳は17年に一度) |
| 志度寺(香川) | 十一面観音菩薩立像 | 毎年7月16日・17日 |
| 竹林寺(高知) | 文殊菩薩騎獅像および四侍者像 | 50年に一度 |
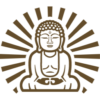
「あなたの地域+秘仏」でネット検索すれば、新たな秘仏が出てくるかもしれませんよ。
解説は以上です。